
仕事をしている女性の方で、妊娠が発覚したときって、仕事をこのまま続けていこうか、妊娠を機に退職しようか迷うところですよね。
もちろん会社の事情や家庭の都合、体調などによって左右されることだとは思いますが、中には規定の日程より早めに仕事を休みたい、または辞めたいたいう人もいると思います。
職種によっては、大きいお腹で仕事を続けるのが難しい場合もありますからね〜。
妊娠したのはいいけど、無理せず早めに仕事を休みたいと考えている妊婦さんは必見ですよ!
妊婦は仕事をいつまで続けるのか法律はどうなってる?
妊娠中というのは、妊娠していないときと比べて、配慮しなくてはいけないことも多くなりますし、体調管理も必要になります。
また、無理ができないということもあってか、妊娠中に仕事をする場合は、労働についてきちんと配慮するよう法律(労働基準法や男女雇用機会均等法)で決まっているんです。
では、最初に具体的にどんなことが定められているかというと…?
- 出産予定日の6週間(多児妊娠の場合は14週間)前は、休業を請求した時にはその者を就業させてはならない。(産前休暇)
- 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせても良い。(産後休暇)
こんな感じになっています。
基本的に、出産前は本人の希望で左右されるような条件ですが、産後については本人が希望しても、どんなに早くても産後6週間以内は就業できないようになっています。
そのため、妊娠が発覚してからいつまで仕事を続ければよいのか?という疑問に対しては、産前休暇を取る場合は、出産予定日の6週間前になれば、お休みすることを請求できるということですね。
逆を言えば、産前休暇については本人の請求次第なので、ギリギリまで働くこともできなくはないんです。
そして、一般的に「産休」と呼ばれる制度は、この産前休暇と産後休暇を合わせたことを意味します。
なので、産休を取得したいと考えている人は、どうしても出産予定日の6週間前にならないと、会社に休暇を請求できないという仕組みになっています。
産休期間中は、お給料は出ませんが、健康保険の方から給与の3分の2が支給されますので、産休を取得したいと考えている妊婦さんって結構多いと思います。
この手当のことを「出産手当金」と言いますが、これについては後の項目で詳しく見ていきましょう!
しかし、産休を取りたいと考えている人の中でも、
産前6週間より前からお休みをもらうことはできないの?
と考えている人もいると思います。
これに関しては、結論から言えば休暇に入ることは可能です。
しかし、注意点は、産休期間中にもらえる出産手当金は、産前6週間から支給されるものなので、それ以前に休んだりした期間は支給されません。
そして、産前6週間より前から休暇に入ることに関しては、会社によって対応は異なると思います。
- 医師より、休暇するよう指示があれば休める(診断書がいる)
- 産前6週間より前から休むことはできるが欠勤扱いになるので、給与はなし。
- 有給を使いきることができる。
など、休むことはできても、その対応というのは会社によってバラバラです。
妊娠中に医師からの診断書などがないと会社に休みを申請しにくいケースもあると思います。
そんな方は以下の記事も参考にしてみてくださいね!

また、妊婦さんに対して良心的な会社だと、就業規則などで妊娠中の女性に対して手厚いサポートがある場合もあります!
妊娠中の就業については、法律で決まっていることはありますが、その時の体調や医師の指導の下で条件が変わっていくこともありますし、それに対して会社側は配慮して臨機応変に対応してもらわなくてはいけません。
ということで、まずは何よりも休暇については会社へ相談してみるということですね。
妊娠の報告って、お休みをもらったり、お給料の話もしなくてはならないということもあり、ちょっと最初は言いづらいんですよね。
しかし、会社側としては、妊婦さんに対して配慮をするためにも、早めに報告してほしいものなんです。
会社にちょっと妊娠報告しづらいなあ…と考えている人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね!

妊婦は仕事をいつまで続けるのか法律以外で気になる3つのポイント
法律では、出産予定日の6週間(多児妊娠の場合は14週間)前からお休みを請求できるということですが、実際は医師の診断等があれば条件は会社によって異なりますが、お休みを取得することは出来るというのを、前半で見てきました。
そこで気になるのは、妊娠したら、仕事を続けるのがしんどいから休みたいは休みたいんだけど、早めに休暇に入ることで、何かデメリットはないの?ということ。
何も知らないままお休みに入ってしまって、あとからもらえる手当金があったのに、もらえなかった!!なんてことにならないように、休暇を取得しようと考えている女性は、一度以下のことを確認しておきましょう!
妊婦が仕事をいつまで続けるか法律以外のポイント①:出産手当金
出産手当金とは、産休中に会社からお給料がでない女性にたいして、健康保険のほうからお給料の3分の2相当額が支給される手当金のことです。
その手当金がもらえる期間というのは、出産の42日前~出産の56日後までです。
出産手当金というのは、産休を取得する女性がもらえる手当金というイメージが強いのですが、実は以下の条件を満たせば手当金を受給できるんです。
- 会社の健康保険に加入していること。(旦那さんの扶養に入っていたり、国民健康保険に加入しているのはNG!)
- 産休の期間中に、会社から給料が支払われない。
- 健康保険の加入期間が12か月以上であること。
- 出産を機に退職する場合、退職日が出産予定日(または出産日)の42日前より短い。
- 出産を機に退職する場合、退職日に出勤していない。(欠勤でも会社の休業日でも有給でもOK)
ちょっとややこしいですよね~。
本当、こういう制度って難しいです。
私も1人目の出産のときは、いろいろなところへ問い合わせもしましたし、かなりの時間をかけて調べたりしました…。
でも、もらえる手当はもらいたい!!
ということで、私が実際に出産手当金について調べているときに、引っかかったことやわかりづらかった部分をわかりやすく見ていきたいと思います。
産休を取得して出産手当金をもらう場合
産休を取得して、また出産後に落ち着いてから会社に復帰したい!と考えている人。
産休期間中にもらえる出産手当金ですが、これは健康保険法上、支給期間が産前6週間と決められていますので、実際産前6週間より前からお休みに入った場合は、出産手当金は受け取れないということになります。
その代わり、会社によっては独自の手当があったり、有給をつかえたりする場合があるので、そういった場合は、無給ということもなさそうです。
が、有給をすでに消化してしまっているなどの理由から、欠勤扱いになったりして会社から給料が出なかったとしても、出産手当金は受け取れないので注意が必要です。
出産手当金をもらって退職する場合
実は、これって意外と知られていないんですが、退職するから産休を取得する場合にもらえる「出産手当金」はもらえないという認識。
先ほど挙げた条件をちゃんと満たしていれば、退職する場合でもちゃんと出産手当金が受け取れるんです!!
ちなみに、私自身、出産を機に会社を退職したのですが、出産手当金を受け取ることが出来ました。
ただ退職するけど、出産手当金を受け取りたいと思っている場合は、退職日に注意が必要です。
大手の会社に勤めていて、人事の担当の人がいるような会社であれば申請書の用意や、書き方などを指導していただけるかもしれませんが、小さい会社の場合は自分で申請書を用意し、自分で手続きを行う必要があります。
その時は、「健康保険 出産手当金支給申請書」というものが必要になります。
この申請書は、自分で記入するところはもちろんですが、産婦人科の医師か助産師・事業主にも記入してもらう欄がありますので、特に事業主記入欄は、実際に退職する前に記入してもらっておく必要がありますよ!
「健康保険 出産手当金支給申請書」は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでダウンロードすることができます!
また、自分で申請書を用意する必要がある人の中には、退職日の希望を出す際に「出産予定日の42日前って一体何日になるんだ…?」と不安になる人もいるかもしれません。
そんな場合は、カレンダーを1日1日数えていく前に、各県の協会けんぽへ問い合わせをし、出産予定日を伝えると、あちらの特別な計算機でささっと計算して、間違いのない日をわずか数秒で教えてくれますので、相談してみるのも手ですよ!
私も、日にちに間違いがあって支給されないのは嫌だったので、書き方から記入する日付についても何度か問い合わせをしましたが、毎回丁寧に教えてくれたので、そのおかげもあって書類に不備もなくきちんと支給されました!
そのため、自分で申請書を用意する人は、一度不備確認も含めて各県の協会けんぽへ問い合わせしてみることをおススメします。
妊婦が仕事をいつまで続けるか法律以外のポイント②:税金免除
いつまで仕事を続けるかによって税金免除になるかどうかが左右されます。
大きく分けると、産休を取得する場合、つまり産前6週間まで仕事を続ける場合と、退職する場合になります。
産休中には、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の支払いが免除となります。
また、産休期間中は給与の支払いが基本的にはないので、その場合雇用保険や所得税も支払う必要がなくなります。
ただし、住民税だけは注意が必要です。
住民税については、前年度の年収に対して支払う義務がありますので、今現在産休で無収入になったとしても、前年度に収入があれば、住民税を支払う必要があるんですね~。
気になるのは、産休期間中に「確かに会社からの給与は出ていないけど、出産手当金は受け取っている場合って、税金はかからないの?」ということ。
出産手当金や育児休業給付金は給料ではないため、課税対象にならず、非課税になるのでご安心ください!
このように、産休を取得する場合は、産休期間中の税金は免除されますが、退職する場合はその時点で、社会保険などの切り替えをする必要が出てきます。
すなわち、切り替えた時点(退職した時点)から、健康保険などを支払う必要が出てくるケースがあるということです。
健康保険については、以下の選択肢があります。
- 国民健康保険に切り替える。
- 旦那さんの扶養にはいる。
- 在職中の社会保険を任意継続する(2年間)
このどれにするかは、個人によって選択肢が異なると思いますが、誰でも3択から選べるわけではありません!
もちろん旦那さんの扶養に入ることができれば、税金は払わなくても良くなりますが、扶養には奥さんの収入によって入れるか入れないかが決まってきます。
例えば、退職金をもらっていたりして年間の収入が130万円をこえてしまうと扶養に入れない場合もあります。
旦那さんの扶養に入れない場合や、旦那さんが国民健康保険の場合は、自身が国民健康保険に加入することになるのですが、その場合は、切り替えた時点から支払いが発生することになります。
また、あまりいないとは思いますが社会保険を任意継続していく場合も支払いが発生します。
この場合は、今まで会社で負担してくれていた分も自己負担になりますので、さらに支払い額が大きくなります。
あまりメリットは感じないですよね…。
そのため、いつまで仕事を続けるか(産休を取得するかしないか)によって、税金の支払い方が変わってきますので、その点も注意が必要です!
妊婦が仕事をいつまで続けるか法律以外のポイント③:会社規定
会社によっては、妊婦さんに対して手厚いサポートが受けられるシステムを導入している場合があります。
それは、妊娠中に仕事に従事している期間や、時間によって変わってくる場合も考えられます。
そのような会社の独自システムを利用したいと考えている人は、退職日も含めて会社とよく相談してみてくださいね。
妊婦が仕事をいつまで続けるか法律以外の判断基準
さて、今まで難しい部分も見てきましたが、要はいつまで仕事をするかによって税金や産休の取得について条件が変わってくるということです。
妊娠していつまで仕事を続けようか、または規定よりも早く仕事を休みたい、退職したいと考えている人は、ここまでの内容を確認した上で、決めてくださいね!
個人的に思うのは、仕事を続けるか続けないかの判断基準は、第一に体調だと思います。
実は、私の場合ですが妊娠を機に旦那の自営業の手伝いをすることにしたので、退職することを選択しました。
しかし、前述した通り、会社は退職するけど、条件を満たしていたので出産手当金は受給するつもりでした。
出産手当金を取得するためには、退職日が出産予定日(または出産日)の42日前より短い必要があります。
なので、私はその日まで働くつもりだったのですが、途中で切迫流産と診断され出産日まで入院することになってしまったのです。
イコール、その時点から会社へは行けなくなったので、そのまま退職するしかなくなり出産手当金はもらえないな、と思っていたのですが、会社側が配慮してくれて、一応出産の1ヶ月前までは在職しているという扱いにしてくれたのです!
そのおかげで、入院していたにも関わらず出産手当金を受給することができましたので、会社のおかげです。
そのため、体調が悪かったり医師の指導があって仕事が続けられないから、出産手当金や産休の取得が難しいかなぁ…と考えている方も一度会社に相談所してみることで、良心的に対応してくれる場合もありますよ!
まとめ
妊娠すると思うように体が動かなくなるため、普段と同じように仕事を続けているモチベーションではなくなったりするんですよね。
しかし、お金のこともあるから、なかなか悠長なことも言ってられない…!
という、気持ちもすごーくよくわかります。
ただ、そこで無理をしてしまうと私のように入院生活を余儀なくされた立場から考えると、やはり無理は禁物だな、と思います。
ちなみに、妊娠を機に自宅で仕事をするという選択肢もありますよ。
会社勤めは通勤も含めてちょっと辛いけど、自宅でなら仕事をしてもいいかも!と思っている人は、以下の記事も参考にしてみてください。

仕事を続けるか休むかという選択肢には、いろんな葛藤があると思いますが、まずは法律の観点からと、お金や税金の問題、全てきちんと把握した上でお休みをとるか、頑張って仕事を続けていくかを検討してみてくださいね〜。
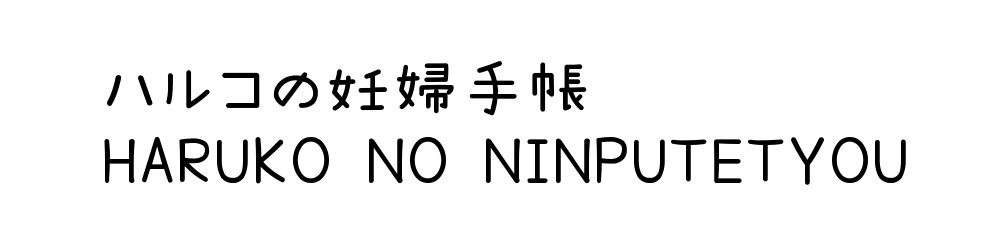

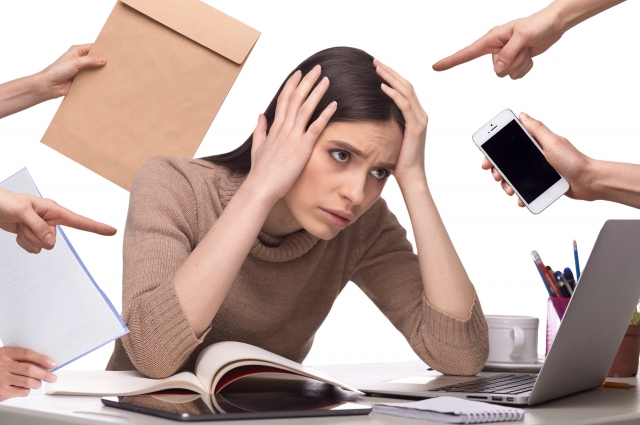
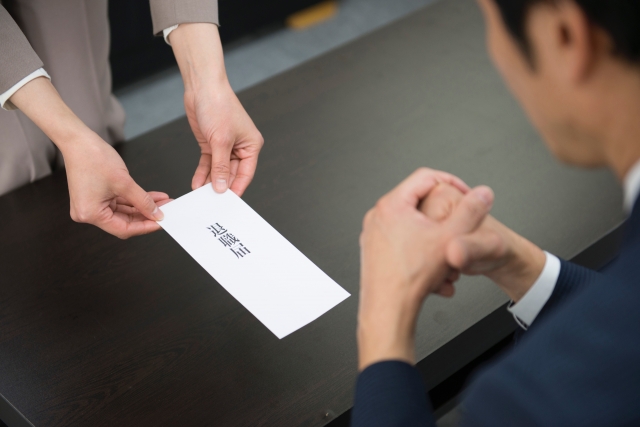
コメント